「理解する」「わかる」ってどんな状態?不正解の問題は「理解」を深めて長期記憶にする
「理解する」って具体的にどんな状態なのでしょうか?
時間をかけて勉強しても、常にこの状態まで到達しているわけではありません。
それは「自分の言葉でひとに説明できる」、
もしくは「自分の脳内で映像が再生される」という状態だと思っています。
自分が受験勉強をしていたころ、
「わかるようになるまで」とか、
「自分が納得するまで・理解するまで」ということをよくいわれました。
正直いわれたときはあんまりピンときていませんでした。
しかし、当時のセンター試験(現・共通テスト)がせまってきていた冬、
勉強も深まってきたころに、ようやく自分の中で納得できたのを覚えています。
20年ほど経ったいまでも人生の記憶に残る大きな「気づき」でした。
それがわかってからというもの、
理解できるまで「考え抜く」ことを大切にするようになりました。
正直覚えることが多すぎて、暗記だけにとどまった言葉も多くありました。
限られた時間の中で、
どうしても定着しないことや何度も間違えてしまう問題に対しては、
自分が理解するまで調べたり、考え抜きました。
そこまでやり抜くと、
長期記憶として自分の中に残り忘れにくくなりました。
では、「理解する」にはどうすればいいのか?
たとえば世界史の勉強では
多くの人物名・地名を覚えなくてはいけません。
教科書の文章を読んだとき、
その内容を友人や家族にわかるように説明できるでしょうか?
それを自分の言葉で噛み砕いて説明できたとき、
または、自分の脳内でその歴史イベントの情景がひろがり映像のように再生されたとき、
その状態は、「理解した」という点まで到達できているんだと思います。
具体的な勉強法は人によりけりだと思います。
自分自身の体験としては、
イメージとストーリーで理解することが大きな助けとなりました。
世界史をテーマにした漫画を読む。
地名が出てくる場合は教科書や資料集で地図を調べる。
民族は実際にどこからどこに大移動したのか? →ルートを地図で見る。
ナポレオンはどの範囲まで攻略したのか? →ルートを地図で見る。
アルザス・ロレーヌ地方とはどの位置にあるのか?→地図で見る。
文化史ではルネサンス時代に描かれた絵画はどのようなものかや
建築様式はどのようなものかなど。 →図録で実際に見る。
勉強に夢中になっていたときには
資料集や参考書のイラストや写真をハサミで切って
自分用の世界史まとめノートに貼り付けたりしていました。
いまですと、Googleの画像検索も役に立つのではないでしょうか。
教科書に載っているのであればそれがいちばん信頼できると思います。
まとめ
「理解する」「わかる」ためには、
【自分の言葉で説明できる】という状態を目指せば、
おのずとできるようになるのではないかと思っています。
友人や家族・兄弟、同級生や塾の先生に聞いてもらってもいいと思います。
ブログやSNS、日記やノートに落とし込むのでもいいと思います。
その状態にするためにどんな情報が必要か?と自分に問いながら、
着々と自分で納得できるものを増やしていくと、
試験ですいすいと解ける問題が増え、勉強が加速的に楽しくなっていきます。






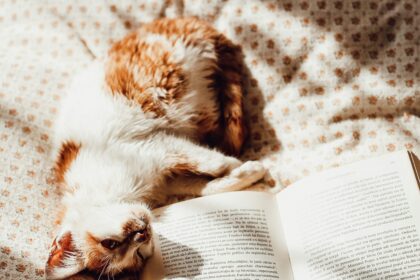


コメントを残す